img-clip.nvim がブログを書くときの画像貼り付けの面倒さから解放してくれた
ブログの記事を Neovim で書くようになりそれなりに時間が経ちました。使い慣れたエディタでブログを書けるのは多くの面で快適で心地よいのですが、記事内の画像の挿入だけはものすごく面倒に感じていました 。
この1点のデメリットが大きく、ドラッグアンドドロップで済む Web ベースのブログエディタに戻ろうかと何度か考えたこともあります。
そんな折、img-clip.nvim というプラグインに偶然出会い、この圧倒的に面倒な作業から解放してくれたので、感謝を込めて紹介します。
画像挿入のなにが面倒か
画像を挿入するには次のような手順を踏む必要がありました
- スクリーンショットを撮るなどして貼り付けたい画像を取得
- ブログの画像ディレクトリ
content/assets/以下に移動 - 画像ファイルを、本ブログのルールに合わせてリネーム
2025-10-22-article-name-01.pngのような規則
- ブログ記事側から、Markdown記法で画像パスを記述
のように
どのステップも地味に面倒で、数が増えるほどに面倒さが重なっていきます。ファイル名を考えるのが面倒なので一定のルールを考えたものの、そのルールに沿って作業するのもまた面倒でした。
img-clip.nvim の効果
img-clip.nvim は、クリップボードから直接画像を貼り付けられるNeovimプラグインです。
"Effortlessly embed images into any markup language" とあるように、Markdown に限らず LaTeX、Typstなどのファイルにも画像を簡単に挿入できます。
私の場合、上述の4ステップが1ステップ(1コマンド)で終わるようになりました。以下がそのデモです。
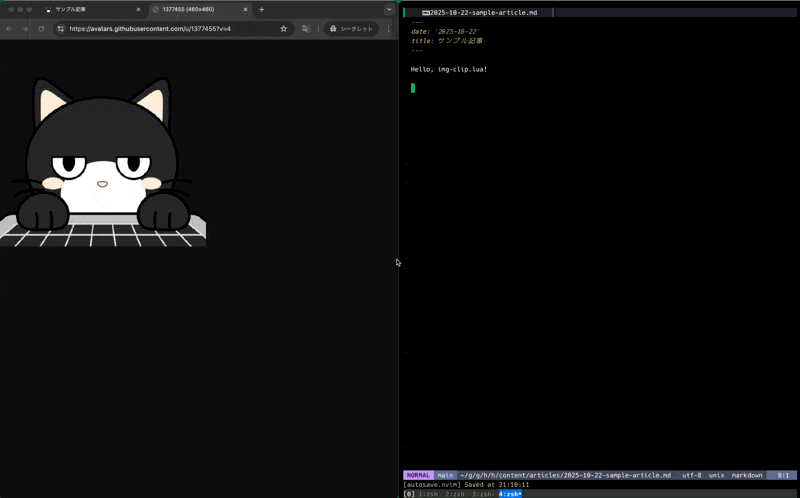
スクリーンショットを撮ってクリップボードに保存したら、それを img-clip.nvim の :PasteImage コマンドで貼り付けるだけです。これだけで、適切なディレクトリに適切な名前で保存され、適切な形式で markdown の記法で追記してくれています。
このブログでの設定
ありがたいことに img-clip.nvim はプロジェクトのディレクトリのルートに .img-clip.lua というファイルを配置することでプロジェクト固有の設定を適用することができます。
私のブログでは、以下のような設定をしています:
-- .img-clip.lua
return {
default = {
prompt_for_file_name = false,
dir_path = "content/assets",
file_name = function()
local current_buf_name_without_ext = vim.fn.expand("%:t:r")
return current_buf_name_without_ext .. "-%Y%m%d%H%M%S"
end,
},
}これだけの設定で、以下のような動きにできます
:PasteImageで貼り付けると、画像は自動的にcontent/assets/以下に保存される- ファイル名は
記事ファイル名 + 現在日時として自動的にセットされる- 結果的に
content/assets/2025-10-22-efficient-image-workflow-with-img-clip-nvim-20251022212044.pngのようなファイルが追加される
- 結果的に
さらにMarkdown記法で caption にカーソルが当たった状態で書き込んでくれるのですぐに執筆作業が続けられるところも嬉しいですね。
まとめ
img-clip.nvim のおかげで、ブログ執筆時の画像挿入の嫌な手間から解放されました。
Before
スクショ撮影
↓
ファイルを所定のディレクトリに移動
↓
ファイル名をリネーム
↓
Markdown記法を手入力After
スクショ撮影
↓
:PasteImage で貼り付け正直なところ画像の挿入が面倒すぎてブログを書くのも少し嫌になっていたのではと思うくらいです。
インストールと簡単な設定だけで使い始められるので、同じように Neovim でブログを書いていて画像貼り付けに対して同じ気持ちの方はぜひ試してみてほしいプラグインです。
以上、感謝を込めてプラグインの紹介でした。 Thank you! img-clip.nvim!

h3pei
フリーランスのソフトウェアエンジニア。Ruby / Rails アプリケーションの開発が得意領域。設計・実装・運用まで含めてプロダクト開発が好きです。
Questalという目標達成コミュニティサービスを開発しました。仲間と一緒に目標達成に取り組みたい方はぜひご利用ください。